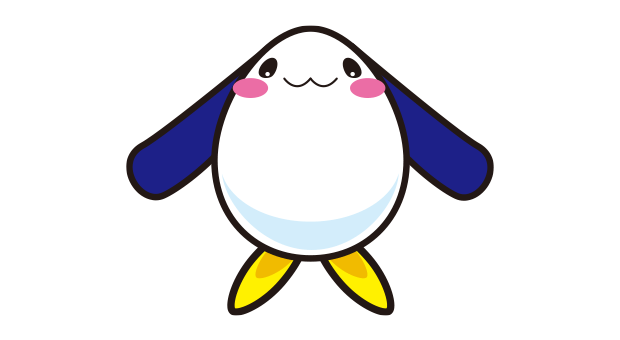岡山は、名君といわれた池田光政の時代を中心に熊沢蕃山と津田永忠という叡智を持った家臣により、教育的、経済的にも大きな発展を遂げたことは周知の事実ですが、前回の蕃山に続き、今回は津田永忠についてご紹介しましょう。
津田永忠は、全国でも屈指の大名庭園であり、日本三名園のひとつである「後楽園」の造営、藩校石山仮学校・閑谷学校、吉備津彦神社の造営、和意谷墓所・曹源寺の造営など教育・文化の面の功績、そして倉田・幸島・沖の新田開発、百間川の開鑿など、数多くの業績を遺しています。
これら功績ののひとつが、農林水産省のサイトに、「2,800haを超え新田を開いた津田永忠」として紹介されていますので引用することとしましょう。
《沖新田の干拓と百間川の開削》
岡山県岡山市/1640年(寛永17年)~1707年(宝永4年)
岡山県の南部に広がる岡山平野の約2万5千ヘクタールの田畑のうち、約2万ヘクタールが干拓によって、造られたものです。特に、江戸時代の「沖新田」の干拓は、規模が大きく、百間川の開削が一緒におこなわれたという特徴があります。
当時は、岡山の城下を流れる旭川は川が浅く、たびたび、洪水の被害が発生しました。また、米の取れる量も現在に比べ少なく、日照りや洪水により饉もたびたび、起こっていました。
1654年に熊山蕃山が旭川の洪水を防ぐため、新たな川を掘ることを考案し、1669年に蕃山の弟子の津田永忠により川の掘削が行われ、現在の百間川ができあがりました。このことにより、洪水被害から町や村を守ることができるようになりました。
また、永忠は飢饉を解消するために、新田開発が必要と考え、百間川によって排水ができるようになった河口に広がる沖新田の干潟の干拓を考案します。沖新田干拓では、約12キロメートルの堤防を6ヶ月で完成というハイスピードな工事で、約1,900ヘクタールの新田開発が実現しました。
この他に、永忠は、倉田新田(360ヘクタール)、幸島新田(600ヘクタール)を手がけ、2,800ヘクタールを超える新田を生み出し、さかんに農業が行われました。
この他の、農業土木に関する業績としては、田原井堰の建設、倉安川の開削などがあります。また、永忠は、後楽園の造園、閑谷学校の建築をはじめ藩政改革・財政再建と、めざましい業績を残しています。
熊沢蕃山とその弟子であった津田永忠は、その政策で対立することはあったものの、岡山藩初期における大きな役割を果たしたことを、ご理解いただけるかと思います。
では池田光政が津田永忠の才能を評価していたことからお話しましょう。
永忠が16~17歳の頃のことです。
何と寝ずの番の任についていた時、光政から自鳴鐘(時計)が、何時を知らせたのかと問われたときに、「寝ていたので存じ上げません」と答えました。
さすがに光政も呆れて言葉が出なかったのでしょうか。やがて夜が明けて、永忠が傲慢な態度で立ち去るのを見て、「事をなすべき男なり」と独り言を呟いたといわれます。
さらに小姓横目などの任についていた18歳の頃、身分の高い執政達が光政邸での評定の後、世間話などに花を咲かせている時に、永忠が近寄ってきて、「ここは長話をする所ではありません」と誡めました。さすがに20歳にもならない若輩の謗りに激怒した老臣たちは、光政にこのことを告げますが、光政から帰ってきた言葉は、「さては自分が見る所と違わず、心に思う事を憚る所なく、述べる者と思っていたが、まさにその通りだった」だったと述べたと言われています。
また光政は、「彼者は、使ひやう悪しくば國の禍をなすべし、才は國中にならぶ者なし」と述べていることから、永忠の資質を大いに評価し、使い方さえ誤らなければ、その才能は藩に並ぶ者がいないほど最高のものと考えていたようです。
熊沢蕃山言行録の中で、この熊沢蕃山と津田永忠を使い分けた光政を評して、「斯る過激者(永忠)と、蕃山の如き温和者を用ゐたのは真に王者としての大度量を示すもの」と書いています。
もちろん熊沢蕃山と津田永忠は、20以上も歳が離れていたこともありますが、蕃山が深慮の実業家だったことも、大きな違いでしょうか。
このことを熊沢蕃山の言葉から引用します。
一の不義を行ひ、一つの不幸を殺して天下を得ることもせざるは朱子王子変りなく候。拙者世俗の習未だ免かれずと雖も、此の一時天地神明に質しても古人に耻づべからず。
この言葉から、熊沢蕃山が、一つの政策を遂行する際にも、一の不義、一つの不幸を行うことを決して許さず、たとえ些細なことであっても犠牲を払うことを極力避けたています。
この蕃山は治水・山林事業において名を馳せたものの、その思い描いた創意は、後に稀代の才人・津田永忠により、新田開発などの事業が行われることとなりました。
では沖新田開発にあたっての永忠の真意を見てみることとしましょう。
名を好候ヘハ沖新田之儀ハ取立不申候 倉田新田 幸島新田ニて 私名ノ爲ニハ能御座候 首尾可仕も慥ニハ不被存 二ツ物かけ成 沖新田ハ取立不申候 五穀ノ出来不申候處ヲ 人力ヲ以五穀出来仕日本ノ食物増候様ニ被 仰付ハ天道又ハ天下ヘノ御奉行と奉存候 又ハ沖新田御普請又は此後沖新田ニたより渡世仕ル者幾人と申事御座有ましくと奉存候 天道之意味ハかやうノ事と承傳候
天道は、天地自然の法則を意味する言葉ですが、永忠は、もともと耕作に適さない土地を人の手を加えることにより、お米の増産が出来るようになると述べています。
永忠は、水害・旱魃に苦しむ土地を調べ、堤防・潅漑・池沼・溝渠などを整備することにより、荒地を実り多き土地に生まれ変わらせました。そして、この新田開発の経費は、以前ご紹介しました「社倉米」の利益から行われています。
このほか、山林・竹林等の濫伐を禁止したり、宅地には桑・麻を植えさせるなど、さまざまなことを行っています。
この永忠が、政治にかけた思いを岡山藩家老・日置猪右衛門宛の意見書(一部抜粋)から見てみることにしましょう。
私之儀ハ始終御國ノ御爲ヲ存一生ノ内抽忠義ヲ盡し度大望ニ奉存候ニ付何もかも打捨申上候 御上の御勢ノ不宜ほと私ハかやうニ不存候ハて不叶わけ御座候 本道理ハ
御上御先代ノことく有之其ヲ奉請御役人共はけみ候埒にて御座候へ共 其段ニハ及無御座候へハせめて御自分様次ニハ御用人中並私躰もいかやうニ苦ミ候て成共御奉公申上ル時節と奉存候 主人親之順なるニ忠孝ハ其筈之儀ニ御座候 不順ニ出合其志ヲ立候事誠ノ忠孝と承候 其段は兼而申上ル楠殿能手本と奉存候
(途中省略)
私身代格式此上之望可有御座様無御座候 尤出頭之望も無御座候 いかやうニ私事御耳に立居申候共たいてい只今ノ通ニて兼而申上ル通今五六年何とそ相勤申度候
(以下省略)
この意見書からも、永忠が刻苦奮闘し、藩政を推進する表れが見て取れますし、これ以上の立身出世を望まないことも書かれてあります。
家老・日置草也の言葉に、永忠を評して、
佐源太は剛直忠良の人といふべし。苟も理を害するものあれば、執政と雖も少しも争うて枉げず。往復三回に及ぶも、未だ止めず。此の如きの人なし。若しあらば佐源太と共に事を伺うして、國家を裨補すること大ならんに、惜いかな佐源太一人のみと。
また永忠も「天も地にも依頼すべきは日置老のみ」と述べていることから、日置家老と永忠の深い信頼関係がうかがえます。
津田永忠の業績を一部ご紹介しましたが、百間川・倉安川、そして後楽園など、今でも私たちの前にその偉業を見ることが出来ます。
偉人の業績を脳裡に浮かべながら、改めて巡るのも良いですね。
《参照》
・出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/museum/m_izin/okayama/
・池田光政公伝. 上巻/石坂善次郎 編/石坂善次郎/昭和7(1932)
・池田光政公伝. 下巻/石坂善次郎 編/石坂善次郎/昭和7(1932)
・熊沢蕃山言行録/畠山秋更 著/東亜堂書房/大正6(1917)
・岡山市史/岡山市 編/岡山市/大正9(1920)